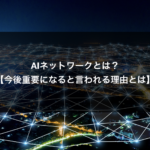近代都市を象徴する超高層ビルや過密な人口や都市機能。利便性と同時にストレスを与える街づくりからの反省からか、都市やコミュニティのあり方が見直されている。
近年注目を浴びるのが、スマートシティ、あるいはスマートコミュニティと呼ばれる都市形態だ。生活や仕事をする人間にとってやさしい街づくりが求められている。このスマートシティ建設に不可欠なのがAI(人工知能)である。
続きを読むスマートシティとは
スマートシティは、都市建設と切り離せない。その歴史は数千年に及ぶ。そこで都市づくりについて最初に説明したい。
都市づくりの歴史
都市が形成されたのは、紀元前3000年頃の古代メソポタミア時代まで遡ることができる。都市と村落との違いは、支配層が統治するための拠点かどうかである。戦争に必要な軍隊を収容する城塞、神事を行なう宮殿などが都市に併設されることで、その機能を強化してきた。それだけでなく象徴としての都市は文化を反映し、バロック様式の建築物や幾何学模様を描く道路など、最先端の技術や芸術、文化の粋を結集した存在だったともいえる。
20世紀の都市づくりで象徴な存在は、超高層ビルや地下鉄などの交通機関だろう。生産性を高めるために、交通インフラなどを整備するだけでなく、都市機能が一部のエリアに集中された。結果として、混雑する鉄道や道路渋滞、大気汚染など、人々にとってストレスフルな環境になるという副作用も生じた。
このような反省から、人間にとってやさしい街づくりが求められるようになった。このような街づくりの歴史が、スマートシティの根本にある背景にあるともいえよう。
スマートグリッドから発展したスマートシティ
都市づくりのあり方を変えるスマートシティのアイディアは、意外なところから現れてきた。それは電力業界だ。2009年に米オバマ大統領によって、グリーンニューディール政策が発表された。エネルギー利用効率の向上や再生可能エネルギーの導入促進などが同政策で掲げられている。この一環で、電力インフラの信頼性を向上させ、効率的に電気を供給する設備の更新や増築が行われた。この際、スマートグリッドに不可欠なスマートメーターなどの実現にIT技術が応用されたのだ。
「スマート」が頭に付く用語には、スマートフォンやスマートウォッチなどIoT(モノのインターネット)を想起させるのが多い。スマートシティの定義はないものの、スマートシティの由来はスマートグリッド構想にある。電力インフラの効率化を目指したスマートグリッドを、都市インフラにまで拡張しようというのだ。そのためには、交通網やゴミ処理、下水道や都市の配置といった都市機能の効率化が必要になる。
AIとスマートシティの関係性とは
スマートグリッドでも活用された「モノ」のインターネット
スマートグリッドがそうであるように、スマートシティ実現のためにはIT技術が不可欠である。事実、スマートグリッドは、グーグルやマイクロソフト、シスコやGEといったITとの関連の深い大企業やベンチャー企業によってけん引されている。
IT技術のなかでも、近年注目を浴びるAI(人工知能)。その威力は、IoT(モノのインターネット)によって発揮されるといって過言ではない。ネットワークに接続された端末からデータを受信し、そのデータをネットワークに属するあらゆる「モノ」の機能の効率化に役立てようというIoT。
見える化したデータを都市機能の効率化に活かすAI
ネットワークに端末を接続させるアイディア自体は、IoTが注目される以前からスマートグリッドで実現されていた。たとえば、スマートグリッドを代表する機器に「スマートメーター」がある。電力のメーターに搭載された通信機能を介して、電力使用量が電力会社へと送信される。これらのデータをもとに効率的に電力供給を行なうというのが、スマートグリッドの骨子である。
スマートグリッドによる電力供給の効率化は、AIやIoTの登場によってさらに発展できる。電力インフラを含めた都市インフラを効率化するためには、あらゆる情報が活用されねばならない。そのようなデータを取得するには、端末や都市のスポット等にカメラやセンサーを取り付け、データを「見える化」する必要がある。このビッグデータをもとに、効率的な都市づくりを行なうのがAIの役目である。
スマートシティでAIはどのように活用されるのか
都市インフラの効率化がAIの役目
スマートシティの目指す先には、都市インフラの効率化や住民にとってやさしいコミュニティの実現がある。そのために必要な施策には、以下が挙げられる。
・電力供給を効率化し省エネルギーを実現
・交通網の効率化し脱自動車社会を実現
・ゴミ処理を効率化し二酸化炭素の排出量を削減
・上下水道インフラの安定化
・ヒートアイランド現象の解消やストレスフルな環境に役立つ緑環境の整備
これら都市インフラの効率化に不可欠なのが、AIである。
具体例として電力供給を取り上げよう。日本では発電を、石炭や石油による火力発電、原子力発電などに多くを依存する一方、太陽光発電や風力発電など環境にやさしいエネルギーが注目を浴びている。だが太陽光発電は昼間しか発電できない、蓄電池のコストが高いというデメリットをもつ。そのため、多くのリソースから効率的に電気を使い分ける必要がある。そこで登場するのがAIだ。需要家機器をネットワークに接続し、データを収集。AIがデータ処理することで、自動的に電力供給の調節が可能になる。
交通網の効率化もスマートシティのカギ
交通網の面からいえば、近年着目されているのがシェアリングエコノミー。一台の車を複数人で共有することで、走行する自動車数の削減が期待される。日本でも東京や大阪などの大都市では、交通渋滞が長年問題視されている。シェアリングエコノミーによって走行する自動車の数を減らすことができれば、交通渋滞も緩和できる。
シェアリングエコノミーにもAIの活用が可能だ。たとえばライドシェアのプラットフォームを提供するウーバー(Uber)では、ユーザーが最短経路で目的地にたどり着くためのスケジュールを、走行する自動車から収集されたデータをもとにAIが算出している。またGoogleからスピンアウトしたWaymoは自動運転による配車サービスを手掛けている。自動運転にはAIが活用されるのは周知かもしれないが、Googleはスマートシティ実現という広い観点からWaymo事業に取り組んでいる。効率的な自動車の運用により、道路に割り当てる面積が縮小すれば、その分公園など住民にやさしいスペースが生まれる。裏を返せば、電力事業や自動車事業など個別で考えるのではなく、都市というひとつの機能のもとで統合的に効率化することで、人間にとってやさしい街づくりが可能になるのだ。その手助けをするのが、AIといっても過言ではないだろう。
柏の葉スマートシティコンソーシアムの紹介
千葉市柏市が掲げるスマートシティ建設プロジェクトが「柏の葉スマートシティコンソーシアム」だ。
政府が掲げるソサエティ5.0のモデルプロジェクトに認定
柏の葉キャンパス駅周辺には、東京大学や千葉大学、国立がん研究センター東病院などの施設が存在する。柏市はこのエリアのさらなる発展を目指し、三井不動産とともにこのプロジェクトを立ち上げた。この先進的なプロジェクトは、国土交通省が掲げる「ソサエティ5.0」実現に向けたスマートシティモデル事業の先行モデルプロジェクトにも選ばれた。
ソサエティ5.0とは、IoTによって産業やモビリティの効率化、健康・医療・介護の行き届いた人間にやさしい社会づくりを目指す官庁主導のプロジェクトである。柏の葉スマートシティコンソーシアムは、ソサエティ5.0の思想を体現したモデルケースともいえよう。
柏の葉スマートシティコンソーシアムが掲げる数値目標
柏の葉スマートシティコンソーシアムでは、
・緑被率40パーセントの維持
・二酸化炭素排出量を35パーセント削減
・自転車分担率を10パーセント増加
・自動車分担率を10パーセント低下
など数値目標が掲げられている。これらを実現するために、データ収集やAIの解析が行われる。
自動運転バスの運行は2020年から本格稼働し、交通状況をセンサーでモニタリングし、移動サービスを展開してゆくという。このようなセンシング技術はパブリックスペースにも多数設置される。混雑状況や高齢者の見守りをカメラによって撮影、AIで解析することで改善に役立てようとする。このほかにも、ウェアラブルデバイス等から活動量を計測し、そのデータを解析し、健康増進を対象住民に促すなど、健康サービスにも力をいれる。
だがAIの活用で中心となるのが、エネルギー分野だろう。柏の葉スマートシティでも、スマートグリッドに向けた取り組みが行われる。太陽光発電やバイオマス発電、大型蓄電器などを設置。「AEMS」と呼ばれるエネルギー管理システムを活用し、エネルギーの効率化が図られる。これらの管理がAIを含めたIT技術によって行われる。
まとめ
スマートシティ構想は世界各地で実施されている。とりわけ北米やヨーロッパ、中国などで盛んに推進されている。海外と比較し、スマートシティづくりをけん引する担い手が見えにくいという問題が日本にはあるものの、柏の葉スマートシティのような先進的なプロジェクトも誕生している。今後を期待したい。
<参考>
- 「Society5.0」の実現に向けた国土交通省のスマートシティモデル事業に選定(三井不動産)
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2019/0605_02/ - 「柏の葉スマートシティプロジェクトの取り組み」(『技術と経済』2015年9月号)
- 取り組みが進む次世代都市「スマートシティ」(『Monthly Review』2013年5月号)
- 『初学者のための都市工学入門』(高見沢実 著)
- 『スマートシティはどうつくる?』(山村真司 著)
- 『スマートグリッド解体新書』(日刊工業新聞特別取材班 編)
役にたったらいいね!
してください
No related posts.