AI(Artificial Intelligence:人工知能)は、最近、連日のようにマスメディアで取り上げられているとおり、自動運転や画像解析などの分野で、すでに実用段階に入っている。
とはいえ、AIは単純な概念ではない。そのため、改めて「AIとは何か?」と尋ねられると、明確には答えられないという人も多いだろう。
また、AIのことを調べていくと、アルゴリズム、ディープラーニング、ニューラルネットワーク・・・など、聞きなれない言葉が次々に登場する。少なくともこれらの基本用語は理解しておきたいが、いまさら周囲に聞くのも気が引けるという声も耳にする。
ここでは、AIについて最低限押さえておきたいポイントを取り上げ、解説する。
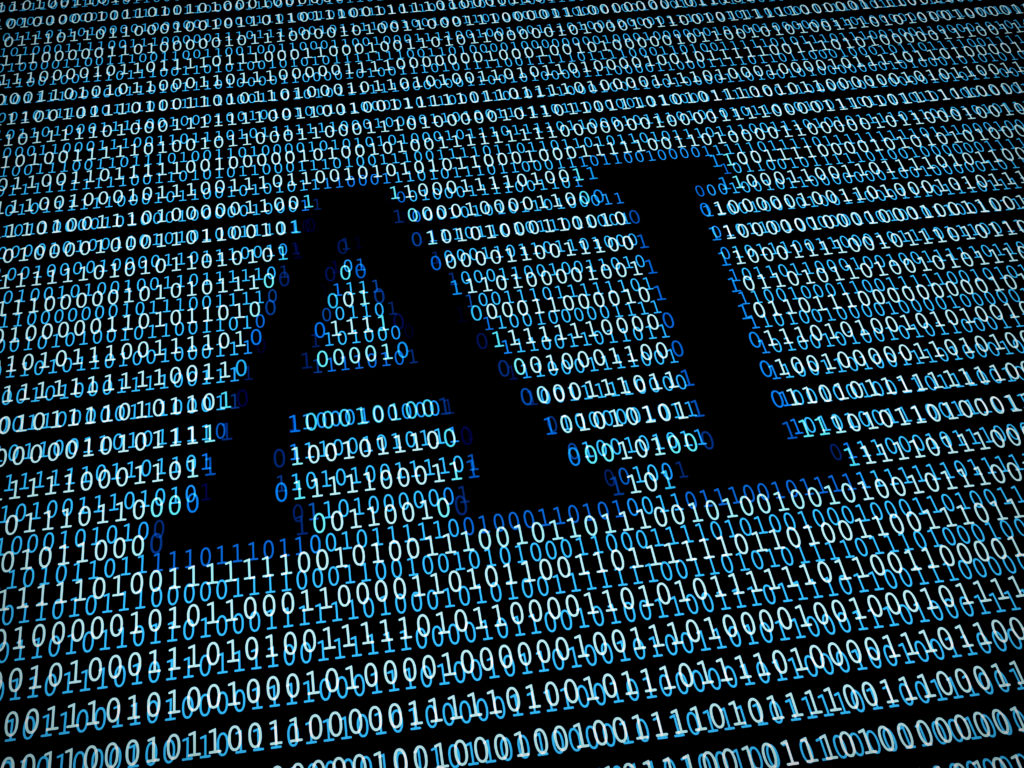
AI(人工知能)の定義
AIという言葉は、すでに我々の生活に溶け込み、それほど珍しいものではなくなった。しかし、必ずしもその定義が統一されているわけではない。
「知能のある機械」という定義もあれば、「人間の頭脳活動を極限までシミュレートするシステム」といった定義もみられる。あるいは「人工的につくられた人間のような知能、ないしはそれをつくる技術」という定義もある。
このように、「機械」「システム」「技術」と定義は異なっていることが分かる。
だが、それぞれ表現は異なるが、人間の頭脳が行うのに近い頭脳労働を担うことができる高度な性能を備えているという点では概ね一致している。そう考えれば、AIとは「人間の頭脳労働の一部を肩代わりするシステムないし技術」であると言うことはできそうだ。
AI(人工知能)研究の歴史
ここで、AI研究の歴史を簡単に振り返ってみたい。
AIという概念が登場したのは、いまから約60年前のことである。1950年、イギリスの数学者、アラン・チューリングが人間とコンピュータの知能を比較検証(チューリングテスト)する論文を発表。それ以来、コンピュータの知能にかかわる研究が活発化し、1956年、アメリカのコンピュータ科学者で、「人工知能の父」と称されるジョン・マッカーシーが、「ダートマス会議」で初めてAIという言葉を使用したとされている。
AI研究は、主に以下の3つのブームを経験している。
第1次AI(人工知能)ブーム(1950年代後半~1960年代後半)
1960年代と言えば、「黄金の60年代」と言われるように、日本も含め、世界的に経済が大きく成長した時期である。
コンピュータについては、すでに、1946年に初期のコンピュータと言われるENIAC(エニアック)が開発され、1964年には「CDC6600」という世界初のスーパーコンピュータが誕生した。
コンピュータという新しい機器の登場とともに、AIの研究も進められた。特に推論や探索ができるようになったことが、第一次ブームの要因とも言われている。ただし、対応できるのはごく単純な問題に限られており、実用化にはまだ程遠いものであった。
第2次AI(人工知能)ブーム(1980年代前半~1980年代半ば)
1980年頃からコンピュータの小型化が進み、企業や一部の家庭にコンピュータが普及し始めた。
第二次ブームを支えたのは、「エキスパートシステム」である。エキスパートシステムとは、エキスパート、すなわち専門家らが有する知識をプログラムに取り込み、意思決定に援用するシステムである。これにより、AIは、知識を与えれば、専門家のような推論や判断を行う水準に達した。
しかし、コンピュータ自らが情報を集めたり、それを蓄積して利用したりといったことはできなかった。また、知識をAIに与えるにもかなりの手間がかかったため、活用の領域は限られていた。
(3)第三次AI(人工知能)ブーム(2000年代~現在)
第三次ブームにおいて大きな役割を果たしているのが、ディープラーニング(深層学習)技術の登場である。この技術によりAI自らが知識を獲得し、より高度な判断が可能となった。
さらに、SNS(Social Networking Service)やIoT(モノのインターネット)などの発達とともに、「ビッグデータ」と呼ばれる膨大なデータが活用できるようになったことも、ブームを後押しする要因となった。
特化型AIと汎用型AIの違いとは?
AIは、カバーする用途に応じて「特化型AI」と「汎用型AI」の2つに大別される。
「特化型AI(Narrow AI)」とは、文字通り何らかの用途に「特化」されたAIである。自動運転や画像の識別など、特定の領域で稼働する。
将棋や囲碁などのAIがその典型例である。グーグルの子会社であるディープ・マインドが開発した囲碁AI「AlphaGo(アルファ碁)」が、2015年10月に世界トップクラスのプロ棋士を初めて打ち負かしたことはよく知られている。最近では、Studio Ousiaが開発した「早押しクイズAI」が、2017年12月に人間のクイズ王チームに圧勝したことが話題となった。
一方、用途を特定せず、多様な機能に対応するのが、「汎用型AI(AGI:Artificial General Intelligence)」である。特化型AIは、一つの機能、例えば囲碁AIなら囲碁に特化してその能力を向上させていくのに対し、汎用型AIは、幅広く多種多様な問題に対応できるという特徴がある。その意味では、「ターミネーター」や「ドラえもん」といった架空のAIロボットは汎用型AIの進化系と位置付けることができるだろう。
なお、用途の幅を基準とした分類とは別に、「どれだけ人間に近いか」という基準による分類もある。「強いAI」「弱いAI」という分類がそれである。これは、アメリカの哲学者で、カリフォルニア大学バークレー校教授のジョン・サール氏が提唱した分類法である。
「強いAI」とは、平たく言えば、人間の知能に近いAIであり、「弱いAI」とは、人間の知能が有する機能の一部を実現できるAIである。「強い」「弱い」という言葉が使われてはいるが、特に優劣を示すものではない。また、人間の知能に近いAIは用途が広い、と考えれば「強いAI」は「汎用型」、「弱いAI」は「特化型」とほぼ同等の概念と捉えることもできよう。
ディープラーニングとは?
上で紹介した第三次人工知能ブームのきっかけとなったのが「ディープラーニング(Deep Learning:深層学習)」と呼ばれる技術である。
ディープラーニングは、「機械学習」のアルゴリズム(答えを導き出す手順)の一つである。
幼い子どもは、たとえ知らない果物でも、その絵や写真を複数見せられると、「リンゴは赤くて丸い」「バナナは黄色くて長細い」などの特徴を見出し、徐々に見分けることができるようになっていく。
このような一定の特徴やルールを数値化したものは「特徴量」と呼ばれる。従来の機械学習においては、特徴量を人間の側で設定する必要があった。しかし、ディープラーニングにおいては、「ニューラルネットワーク」と呼ばれる人間の脳を参考にした神経回路の仕組みが導入されている。これにより、AI自らが特徴量を抽出し、獲得できるようになったのである。
最近では、ニューラルネットワークを多層化することで、より深いレベルでの学習が可能となり、抽象的な特徴量も抽出することができるようになりつつある。そうなれば、今後、AIによる判断の精度が飛躍的に向上し、人類の発展に大きく寄与することが期待できる。
しかしその一方で、「シンギュラリティ」の問題もある。これは、2045年にAIが完全に人間の脳を超える特異点のことである。シンギュラリティの到来により、人間がAIにあらゆる仕事を奪われるとか、人間がAIに支配されるのではないかといった懸念の声も上がっている。
こうした懸念を払しょくするためにも、シンギュラリティの到来までにまだ多少の時間が残されている現時点から、人間とAIの棲み分けや人間によるAIのコントロールに関して十分な対策を検討していく必要があると言えるだろう。
まとめ
以上、AIの定義、歴史、ディープラーニング技術等について解説した。
AIは、すでに自動運転や音声認識、画像解析など様々な分野、場面で実用化が進んでいる。また、ソフトバンクロボティクスのPepper(ペッパー)のような人間の感情を検知するAIを搭載したロボットも実用化されている。
ディープラーニングの登場で、AI自らが膨大なデータから特徴量を抽出し、獲得できるようになった。これにより、今後、AIによる識別や予測の精度が向上し、利活用の幅が格段に広がることが期待される。
シンギュラリティ(AIが完全に人間の脳を超える特異点)の到来に備えて、今から十分な対策を検討しておくべきである。
<参考>
- 人工知能研究(人工知能学会)
https://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIresearch.html - 「人工知能とは(4)」『人工知能学会誌』28巻4号(長尾眞)
- 『眼』をもつロボットが、日本の産業の活路を開く(日経ビジネスオンライン・松尾豊)http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NBO/16/changemakers/interview07_1/
- お答えします スパコンQ&A (富士通)http://www.fujitsu.com/jp/about/businesspolicy/tech/k/qa/s04.html
- 強すぎて「会場がシーンと……」 クイズ王を圧倒した“早押しAI”の衝撃(片渕陽平,IT media)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/28/news037.html
役にたったらいいね!
してください

NISSENデジタルハブは、法人向けにA.Iの活用事例やデータ分析活用事例などの情報を提供しております。






