産業界や世界経済を一変させる起爆剤として、いま、AI(人工知能)が脚光を集めているが、実はこの革新的技術の開発は過去に2度、中断している。
第1次と第2次のAIブームは、いずれも技術的な壁や予算という谷を乗り越えることができず下火になった。現在は、2000年代から始まった第3次AIブームに属する。AIの歴史を振り返ってみると、「使えないから中断した」のではなく、「可能性が無限大だから復活した」ことがわかる。
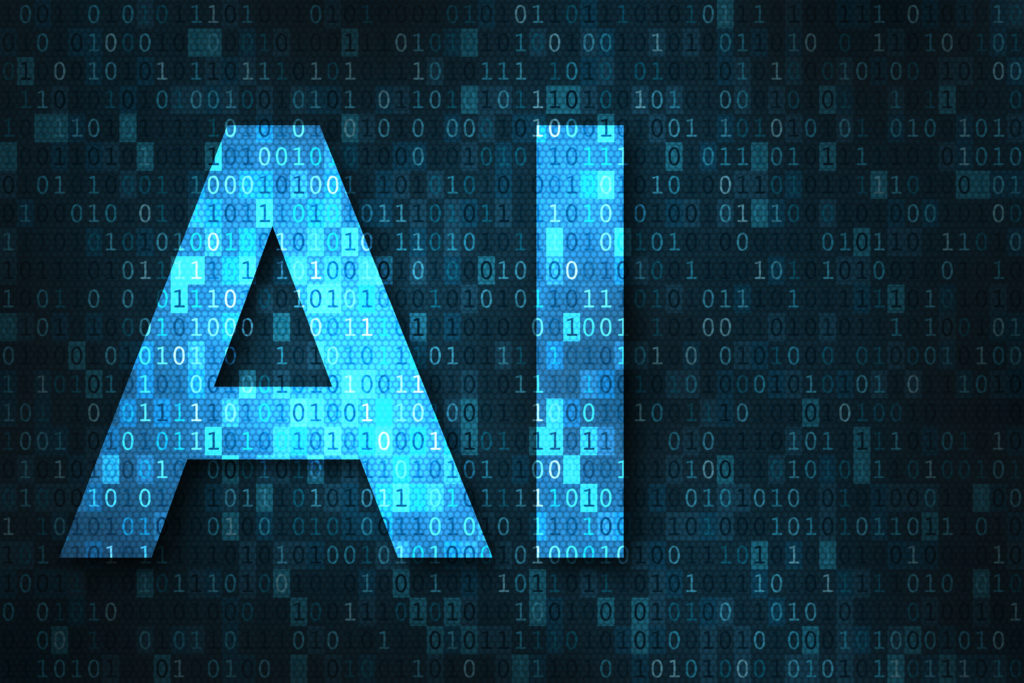
「AIの始まり」チューリングテストとは
AIの概念の起源は、コンピュータ開発の父、アラン・チューリング氏が1950年に提起した「機械は思考できるのか」という問いであるとされている。
チューリング氏は、機械が思考したかどうかは、人との会話が成立したかどうかで判断する、とした。
機械との会話が成立したかどうかの判断は次のように行う。人の審査員が、相手が見えない状況で「人」と「コンピュータ」と対話して、対話した相手が人なのかプログラムなのか言い当てる。審査員がプログラムと対話した後に「『人と』対話した」と間違った答えを出せば、「機械は思考した」ことになる。
これが世にいう「チューリングテスト」である。ただチューリング氏はこのとき「AI」という言葉を使ったわけではない。
チューリングテストに初めて合格したのは、2014年に発表された、ウクライナ在住の13歳の少年が開発したプログラムだった。
1950年から実に64年の時間をかけてコンピュータ技術者はAIのスタートラインに立ったわけである。
第1次AIブーム(1950~1960年代)
第1次AIブームは1950年代後半から1960年代に起きた。この時代のAIの出来事として、次の2点を紹介する。
・ダートマス会議(1956年)
・人工対話システム「イライザ」(1964年)
ダートマス会議(1956年)
ダートマス会議は1956年に米ニューハンプシャー州のダートマス大学で開催された、コンピュータ研究者たちの勉強会である。いまの学会に相当する。
ダートマス会議がAI史に名を残しているのは、同会議の発起人であるジョン・マッカーシー氏がAI(Artificial Intelligence、人工知能)という言葉を初めて使ったからだ。この会議で行われたデモンストレーションは、数学原理をコンピュータで証明することだった。当時のコンピュータはせいぜい四則演算が限界だったため、これは画期的な成果といえた。ただ、「コンピュータが自ら学ぶ」と理解されている現代のAIからするとまったく「AIらしくない」。人との対話チューリングテストも、到底クリアできるレベルではない。
人工対話システム「イライザ」(1966年)
イライザ(ELIZA)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)のジョセフ・ワイゼンバウム氏が1966年に作成した人工対話システムである。イライザによって人類は初めてコンピュータと会話したのである。ただイライザは「考えて回答」しているわけではなかった。例えば人がイライザに「腹が痛い」と言えば、イライザは「なぜ腹が痛いのか?」と返す。これは確かに会話だが、「からくり」があった。イライザに多数の会話パターンを仕込んでおいたのだ。よって、仕込んだパターン以外の質問をイライザにすると、イライザは回答できなくなる。しかしイライザと会話している人が偶然、ワイゼンバウム氏が想定したパターンに則した質問を続けると、見事に会話が成立した。そのため多くの人が「イライザには知性がある」と信じた。
さて、第1次AIブームがしぼんだ理由は諸説あるが、最も説得的なものは「当時の技術ではブレークスルーできなかった」というものだろう。AIの理論も、AIの理論を支える技術も、そしてAIの可能性を信じてお金を出す投資家もいなかったわけである。
第2次AIブーム(1980~1990年代半ば)
第2次AIブームは1980年代に始まり、1990年代半ば終わった。ここで紹介したいのは、日本でのAI事情である。
日本が世界をリード 11年で540億円投資した第5世代プロジェクト
日本政府は1982年から1992年までの11年間に、540億円を投じ第5世代コンピュータ・プロジェクトを推進した。通商産業省(当時、現経済産業省)の管轄下に新世代コンピュータ技術開発機構という財団法人をつくったほどの力の入れようである。最新のコンピュータをつくることは、民間企業の仕事である。そこに税金を投入したのは、日本のメーンの産業に育てようとしたからである。
従来型のノイマン型コンピュータでは、もはや世界に太刀打ちできないという危機感が政官財界で共有された。そこでAIにつながる技術を開発しようと考えたのである。しかしAI開発には多額の費用が必要であり、しかも「明日儲かる技術」ではない。そこで「国策」という形が取られたのである。ちなみにノイマン型コンピュータとは、処理するデータとプログラムをあらかじめ記憶装置に記憶させる形態のコンピュータのことである。
世界1位は獲得した
では第5世代コンピュータ・プロジェクトの成果はどのようなものだったのだろうか。同プロジェクトの最終評価報告書には次のように記されている。
このプロジェクトで開発した「並列推論マシンPIM」は、150MLIPSの推論速度を達成した。LIPSは1秒間に推論処理した回数の単位で、150MLIPSは1億5千万回/秒となる。これは当時の大型コンピュータの100倍の速度に該当し、世界最速を誇った。これは大きな成果といえるだろう。 (一部抜粋)
出所: 第五世代コンピュータ・プロジェクト最終評価報告書 (電子計算機基礎技術開発推進委員会 )
ただAIの「前の前」の段階にまでしか到達しなかった
しかし第5世代コンピュータ・プロジェクトでは、肝心のAI開発には到達していない。先に紹介した最終評価報告書は次のようにまとめている。
・並列記号処理技術が大幅に向上したことによって、知識情報処理技術の応用分野に足を踏み入れることができた
・知識情報処理技術のさらに先に、人工知能を実現する技術がある
ここからは「AIの前段階の前段階に到達した」と読み取ることができる。AIの前段階が「知的情報処理技術」であるが、そこには「足を踏み入れる」だけにとどまっている。AIの前段階(知的情報処理技術)の前段階である「並列記号処理技術」が大幅に向上したにすぎないのである。
当時の限界と次への希望
ただこれは「失敗」には当たらないだろう。なぜならこれが1990年代初頭の限界だったからである。ITは少しあったかもしれないが、ICTもIoTもない時代である。ビッグデータに至っては経済ニュースに用語すら出てこない。ただこの第2次AIブームの中で、次への希望が生まれていた。
差逆伝播法の開発~ニューラルへの道
現代AIの重要キーワードの1つにニューラルネットワークがあるが、これを構築する重要な開発が成功している。ニューラルネットワークについては後述する。
AIにニューラルネットワークを学習させるときのアルゴリズムの1つに誤差逆伝播法(バックプロパゲーション)が必要なのだが、これが開発されたのが1986年、第2次AIブームのさ中であった。
誤差逆伝播法は、誤差を最小化することに役立つ。AIが正しい答えを出すには、まずは人がAIに「正しい入力値」と「正しい出力値」を渡す必要がある。つまりAIに「正しい情報を入手すると正しい答えを導き出せる」という見本を見せ、AIに学習させるわけである。しかし人がAIを使って「便利だ」と感じるためには、AIが、正しいか間違っているかわからない入力値から導き出す出力値と、正しい出力値の誤差を計算し、その誤差を最小にする能力を持たなければならない。なぜなら、人がいつもAIに正しい入力値を渡さなければならないとしたら、何もAIを頼る必要がないからだ。
例えば、AIに1枚の猫の写真を見せて、100枚の猫や犬や牛などの写真の中から、猫だけを、なおかつ猫はすべて選べるようにならなければ、AIとしては使い物にならない。猫も犬もラクダも4本足である。猫と犬は大きさが似ている。白黒の猫と白黒の牛は表面の柄が似ている。しかしとはいえ「猫と犬」「猫と牛」には「誤差」がある。AIが誤差を認知し、誤差を最小化できれば、人と同じように「犬ぐらい大きな白黒の猫」を猫と認識できる。これが誤差逆伝播法である。
バブルの崩壊とパソコンの台頭がAI熱を冷ました
第2次AIブームの最大の成果は、ニューラルネットワークの基礎である誤差逆伝播法などにたどりついたことだろう。
それでもなお、AIは下火になった。なぜか。日本では1990年代前半にバブルが崩壊し、「未来の投資」をする余裕がなくなった。その後遺症は大きく、「失われた20年」が開けた2010年代後半のいま、日本はAI最先端国ではない。また1990年代の世界的なコンピュータ情勢では、マイクロソフトのウィンドウズやアップルのマッキントッシュといったパソコンが主流となり、人々の生活を格段に便利にしていた。コンピュータ業界の資金がパソコンへと向かったためAIの冬の時代が訪れた、という説が説得的だろう。
第3次AIブーム(2000年代~現在)
第3次AIブームは、2006年の「ディープラーニング(深層学習)」の提唱から始まったとされている。
IoT、クラウド、ビッグデータの3本柱がAIを支えた
つまりディープラーニングが第3次AIブームの火付け役といえるのだが、しかしその前提にはIoT、ビッグデータ、クラウドという3大事象の出現がある。
IoTとセンサーによって、情報やデータをいくらでも瞬時に集めることができるようになった。それらをビッグデータとして活用しようという機運が生まれた。さらにクラウドによってビッグデータを「みんなで」活用することができた。第3ブームの現代のAIは、この3本柱によって支えられているので強いのである。
ディープラーニングは機械学習の発展版
ディープラーニングは、機械学習の一種である。ディープラーニングも従来の機械学習も、バナナの写真を見せて「バナナである」と答えることができる。しかし両者ではバナナの認識のさせ方が異なる。
従来の機械学習にバナナを認識させるとき、人間が「細長くて黄色いもの」と教える。それで機械学習はキュウリを見たときに「これは細長いけど黄色ではなく緑色だからバナナではない」と判断する。
しかしディープラーニングはこの上を行く。ディープラーニング型AIには、1,000枚の様々な形態のバナナの写真を見せるだけでよいのだ。するとディープラーニング型AIは自分で「大半は黄色いけど、たまに緑色のバナナもある」「表面はつるつるしている」「黄色い皮をむくと白い身が現れる」といった特徴を抽出する。そのためディープラーニング型AIにキュウリを見せると、「確かにバナナの中にも緑色のものがあったが、それでもこれほど表面がブツブツなものはなかった。ということは、これはバナナではない」と言い当てることができる。
ディープラーニングとニューラルネットワークの関係
ディープラーニングを可能にしたのが、ニューラルネットワークという技術である。
ニューラルネットワークの元の意味は、人間の脳の仕組みのことである。脳が情報を認識できるのは、ニューロンという無数の神経細胞が信号化された情報をやりとりしているからである。
例えば原宿の喫茶店にサソリの精巧な置物があっても、店内がパニックになることはない。しかしサハラ砂漠のテントの中でサソリを見たらパニックに陥る。これは人が、外観だけで物体を判断していないからである。それができるのは、ニューロンが無数の情報を集め、その情報を脳が統合化できるからだ。AIにニューラルネットワークを模した仕組みを導入したことで、AIはディープラーニングという学びの手法を手に入れ、より正確な状況判断能力を獲得したのである。
まとめ
AIには一定のゴール地点がある。それは2045年に到達するというシンギュラリティである。シンギュラリティとは日本語で「技術的特異点」といい、AIが人間の知性を超え生活が一変する世界のことである。ただ自動車、飛行機、テレビ、インターネット、携帯電話などは、一度も技術開発が中断したことがない。それは人々の生活に必要だからだ。
しかしAIは2度も中断している。2045年とは、東京オリンピック・パラリンピックの25年後である。シンギュラリティという「すごい時代」が来るには短いような気がするが、途中で息切れするには十分長い時間といえないだろうか。
<参考>
- IoT・ビッグデータ・AI~ネットワークとデータが創造する新たな価値(総務省)
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc142120.html - 人工知能の歴史(人工知能学会)
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIhistory.html - ダートマス会議(人工知能学会)
http://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AItopics5.html - PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html - 【人工知能はいま 専門家に学ぶ】(8)会話情報学の第一人者、西田豊明氏が見るAIの世界(SankeiBiz)
http://www.sankeibiz.jp/aireport/news/160710/aia1607100700001-n1.htm - 第五世代コンピュータ・プロジェクト最終評価報告書(電子計算機基礎技術開発推進委員会学術的・技術的評価ワーキング・グループ)
https://www.jipdec.or.jp/archives/publications/J0005062 - 「機械学習」と「ディープラーニング」は何が違うのか?(MUGF)
https://innovation.mufg.jp/detail/id=93 - シンギュラリティ(技術特異点)とは(BIZHINT)
https://bizhint.jp/keyword/42911 - 「AIは既に人間の脳の限界を超えている」、茂木健一郎氏(日経×TECH)
http://tech.nikkeibp.co.jp/it/atcl/column/17/052600214/060200012/
役にたったらいいね!
してください

NISSENデジタルハブは、法人向けにA.Iの活用事例やデータ分析活用事例などの情報を提供しております。









